連続育休は、コスパとタイパが良いと感じ、私は年子妊娠を熱望し、実際に年子を出産しました。出産からできるだけ早く社会復帰したいと考える方にとっては、年子はプラスに働くと考えます。早めに第二子以降を出産したいと考え、年子を選択肢の一つとして考えている方の参考になれば幸いです。

タイトルにある単語について、以下を意味しています。
「コスパ」 = コストパフォーマンス / cost performance。費用対効果。
「タイパ」 = タイムパフォーマンス / time performance。時間対効果。
昨今、Z世代を中心に、タイパを重視する傾向があると言われています。
私は、Z世代ではなく、いわゆるゆとり世代ですが、出産適齢期に入っているZ世代の方にも読んでいただけたらという願いを込めて、わかりやすくタイパという単語を使用しました。
ちなみに、「タイパ」という単語を聞くたびに「タコパ」(たこ焼きパーティー)を連想してしまうのは、私だけでしょうか。(おばさん発言でスミマセン汗)
さて、出産や育児について、コスパやタイパといった観点で考えることに、違和感を覚えるかもしれません。
しかし、時間やお金は有限です。
育児にかけられる時間、子どもに費やせるお金も有限です。
もっと言うと、育休を取得できる期間も有限です。
それら時間やお金を使って、できるだけ効率よく、子どもとの時間を確保し、お金を使ってていきたいと常々私は感じ、結果的に年子出産に行きつき、実行しました。
「年子出産による連続育休」とは
働いている場合、一般的に育休を取得できる期間は1~3年と決められています。
それに伴い、延長できる期間も決められています。
それらの具体的な期間は、職場によりますが、
例えば私の職場のように、育休規則で決められている内容が以下の場合で考えてみます。
・育休を取得できる期間:1年
・保育園入所不可の場合、1歳半~2歳まで、育休延長可。
「保育園入所不可」の条件について、お住まいのエリアにもよりますが、4月や10月生まれでない限り、年度途中で空きが出ることは珍しい為、条件に該当するのは比較的容易です。
それを踏まえて上記規則の場合、延長後の育休期間、つまり第一子(上の子)が2歳までに、第二子(下の子)を出産すれば、一度職場復帰せずに第二子(下の子)の産休に入る事ができます。
(以下、便宜上、上の子を「第一子」、下の子を「第二子」と表現します。第二子以降を上の子として年子を出産される/された方は、ご自身の状況に読み替えてお読みください。)
私は、1歳7ヶ月差で年子を出産してますので、上記規則に基づき、第一子育休後、職場復帰をせずに第二子を出産し、連続で育休を取得しました。
「年子出産による連続育休」とは、そのような意味で記しています。
なお、結婚/出産を機に仕事を辞められ、育休を取得しない方の場合、下記コスパの章はあまり参考にならないと思いますので、タイパの章を中心にご覧いただけたらと思います。
コスパ ~可処分所得が多い~
「時短勤務給与ー社会保険料ー所得税ー保育料」vs.「育休給付金」
例えば、2~3歳差で出産する場合に一度職場復帰したとします。
その場合の復帰後の可処分所得、つまり手元に残るお金は、
時短勤務の給与(ex.給与x6h/8h) ー 社会保険料 ー 所得税 ー 保育料
一方、職場復帰をせずに、育休延長して年子出産した場合、
育休給付金(給与x50%)
となります。
理由は、育休中は、社会保険料が免除されますし、育休給付金は所得税の課税対象ではないので、所得税もかかりません。
更に、第一子を自宅保育していれば、保育料もかかりません。
上記3つはいずれも万単位の金額なので、大きな影響です。
育休6か月目以降の育休給付金は、給付割合が67%→50%に下がるので、少ないように感じますが、そこから引かれるものがないことを考えると、手取りや可処分所得という観点では、案外多い気がします。
更に、下記いずれかに該当する場合、育休を取得する数年単位で比較すると、一度職場復帰するよりも、連続育休の場合の方が総可処分所得は多くなりえます。
・育休復帰後の大幅な時短勤務により、時短勤務の給与が育休前の給与(フルタイム勤務時の給与)より大幅に減少する
・育休前は恒常的な残業によりある程度の残業代をもらっていた。育休復帰後に残業をせず、残業代が無くなることで、大幅に給与が減少する
上記に該当する場合、育休復帰後の給与が激減します。
それに伴い、仮にその後妊娠し、育休を取得する場合、次回育休取得時の育休給付金も大幅に減ります。
その理由は、育休給付金は、時短勤務や残業代減少により減少した給与に対し、50~67%の金額が支払われる為、第一子の育休給付金よりも大幅に減るのです。
金銭的な面は以上です。
更に、育休中(子どもと一日中一緒にいる生活) と 職場復帰後の生活(朝晩は子と一緒だが、昼間は就労)のどちらの生活の方が自分は楽しめるのかということも加味すべきかと思います。
例えば、働くよりもできるだけ子と一緒にいたいタイプと、一日中子どもといるよりも合間に仕事している方が精神衛生上安定するタイプがいたとします。
前者の方は連続育休の方が性に合うでしょうが、後者の方は職場復帰した方が心身ともに充実するでしょう。
どちらが良いという話ではなく、育休給付金などの制度と自分の性質の両方を考慮し、家族計画を考えることが、子育てを充実させる一助になるのかなと考えています。
育休給付金と出産手当金の併給
結構マニアックな話ですが、年子出産の場合、第一子育休の取得可能期間と、第二子の産前休暇期間が被ります。
その重複した期間(最大6週間)は、第一子育休給付金と出産手当金両方の支給対象です。
各制度の概要は、以下の通りです。
| 育児休業給付金 | 出産手当金 | |
| 管轄/申請先 | ハローワーク | 健保 |
| 支給金額 | 給与の50% | 給与の85% |
単純に考えると、その重複した期間(最大6週間)において、両者を受給した場合、
50% + 85% = 給与の135%
が受給されることになります。
社会保険料免除や所得税課税対象外であることを加味すると、働いていた当時の手取りの150%くらいになりそうです。
私は連続育休を取得している時、両者を受給する人がいる事に対し、各管轄元はどう考えているのか、興味本位で直接確認しました。笑
すると、両管轄元(ハローワークと健保)ともに、下記主旨の回答でした。
・支給にあたり、W受給しているかの確認を行っていない
・実際、W受給している人がいたとしても、各制度の趣旨は異なるので、特に関与しない。
もちろん、お咎めや支給停止はない。不正受給ではないので逮捕もないだろう。
上記回答は、あくまでも私の所属しているハローワークや健保の回答なので、他のハローワーク等から上記と同様の回答が得られるかはわかりません。
しかし、上記回答より、このW受給が不正受給ではないことは確かだと私は認識しています。
このW受給について、SNS等で世間のご意見を眺めていたところ、不正受給と言っている人もいました。
本人が自分の倫理(?)に基づいて、判断すればいいのかなと思ってます。
私の考えとしては、「制度の趣旨」について、実際のところ、第一子育児もしているし、第二子妊娠/出産もしているので、両者の支給対象には間違いなく該当しています。
ただ、W受給により、通常働いている以上の金額が手元に入ることに問題視される余地があると想像しています。
つまり、どちらかが支給されていれば、生活費は賄えるだろうというご意見があるでしょう。
そういった方は、ご自身が受給しなければ良いだけのお話かと思います。
完全に余談ですが、「子育て罰」「チャイルドペナルティ」という言葉があるように、特に日本で子育てしていくと、今後、多数の理不尽、不平等が待っている訳です。
その前にちょっと多めに受給しても罰はあたらないんじゃないかなと個人的には思っています。
子が一人増えると、その分出費も増えますので、多少のご自身の正義感には目をつむって家計に余裕を持たせてもいいのではと考えます。
タイパ ~育児上の作業量や手間が少ない~
兄弟で一緒に遊ぶことが多い
これは、子の性格に依るかもしれませんが、我が子は8割程度の時間、親が何も言わずとも、二人の世界に入って一緒に遊んでます。
我が子2人は性別が異なるがそこまで多く一緒に遊んでいることを考えると、性別が同じ姉妹や兄弟の場合は、もっと一緒に遊ぶ時間が多くなるのかなと推測しております。
第二子が産まれる前は、私が第一子と一緒に遊ぶ時間が結構あり、子と一緒に遊ぶ時間が長くなると、食事の用意等の家事をする時間が奪われ、結果的に時間に追われてしまいがちでした。
第二子が産まれ1歳以降は、私に「遊んで―」と声がかかることが減りました。
そのおかげで、姉弟が一緒に遊んでいる時間に余裕をもって家事等を先に片付け、自分のタイミングで子の遊びに加わったり、工作等で一緒に遊び道具を作ったりすることができています。
第2子が第1子を見てすぐ真似るので、第二子に教える手間が省ける
トイトレやお箸の持ち方など、第一子は、最近自分ができるようになったことを、第二子に自慢げに話しています。
それにより、私が教えずとも第二子はいつの間にかできるようになり、更に、第一子は第二子に教えることで、自分への更なる定着を図っています。
特に助かっているのは、公共の場で静かにしなきゃいけない、または、うろうろされたら困るケースです。
4歳姉は、私が何も言わずとも、雰囲気を察知して自主的に周囲に合わせて行動しますが、2歳弟は、あえて大声を出しみたり走ったりしがちです。
それを姉が「しーっ」と人差し指を立てて制したり、手をつないだりして、周囲に迷惑をかけない方に動いてくれます。
私が言葉で「静かにして」などと言うよりも、断然効果があります。
このあたりに関しては、下記記事にも記載しているので、よかったらご覧ください。
二人とも満足する遊び場が同一
あらゆる年齢の子どもが満足できる遊び場は意外と少ないと、子育てをして気づかされました。
例えば、我が子は現在幼児2~4歳ですが、その前後1歳差、つまり1~5歳の子をもつ友人と一緒に子を遊ばせたりする際は、特に困りません。
しかし、0歳の子や小学生低学年の子を持つ友人と会う際は、場所に困ります。
1~5歳の子が楽しめる遊び道具では、それ以外の年齢の子楽が楽しめないからです。
公園なら無難かと思いきや、幼児を対象とした遊具と小学生を対象とした遊具では、サイズや高さ、難易度が異なるので、離れた場所に設置されているケースが多くあります。
友人と会うケースで説明しましたが、これを我が子で考えてみましょう。
3歳差以上離れていた場合、子どもどちらかの希望に合わせて行動するか別行動をとる必要が少なからず出てきます。
一方、年子の場合は、遊び場の適応年齢の面で片方の子だけ楽しめない、遊べないという遊び場はまず発生しません。
そういった意味で、行く遊び場への配慮が必要ないので、親としてとても気楽だと感じます。
衣服の管理が楽
1歳差だと、第一子のお下がりを間もなく第二子が着るようになります。
その為、第一子がサイズアウトした服を第二子の衣服棚に収納することになります。
また、第一子が着ていてどんな服がそろっているか自分が認識できているので、第二子が着る際に衣服の過不足を確認する必要がありません。
その為、お下がりを一時的に保管する場所、衣服の過不足の確認する作業が不要です。
我が家は、第一子と第二子の服およびおむつのサイズ差はだいたいワンサイズでしたので、第一子のお下がりや第一子の好みでない服は第二子がすぐに着ていました。
特におむつに関しては、いずれ第二子が使うと考えると、第一子のサイズアウト間近でも気兼ねなく買い溜めできたので、残数をチェックする手間が省けました。
服の処分については、二人とも着るとさすがにぼろぼろ&よれよれになるので、誰かにあげられる状態ではなく、潔く捨てていました。
ちょっと状態が良かったりすると、捨てるのはもったいなく、リサイクル?友人にあげる?と考え、長く保管することになりますが、その点、順に捨てられるのはとても気持ち的に負担が減ったように感じてます。
最後に
本記事では、年子出産および連続育休をコスパやタイパの観点で考察してみました。
自分の人生においてやりたいことが多い私は、育児についてもついついコスパおよびタイパを考えてしまいます。
30代子育て真っ盛りの現在、日々の生活でやりたいことは、
子育てを楽しみたい
会社でキャリアアップしたい
副業も育てたい
日々食べる野菜を自分で育てたい
清潔な家で過ごしたいので掃除もしたい
です。
これを一日24時間の中に少しずつ詰め込むので、どうしても効率思考になります。
特に、コスパの章で触れましたが、「会社でキャリアアップしたい」希望を叶えるにあたり、複数回育休に入るということは、その数だけ保育園の洗礼期間が生じる、つまり、仕事に専念できない期間が長くなります。
となると、楽しいはずの仕事を楽しめないという懸念が私にはありました。
その為、保育園洗礼期間の短縮化、つまり第一子の洗礼期間と第二子の洗礼期間を被らせる=同時に保育園に入園させることで、仕事に専念できるよう、年子プランを考えた訳です。
私の場合、2歳差以上で出産したことがなく、年子方面に思考が偏っていまので、あくまで一例として読んでいただけたら幸いです。
年子計画の詳細については、以下に掲載してますので、良かったらご覧ください。
※
今日も読んでくれてありがとう☀
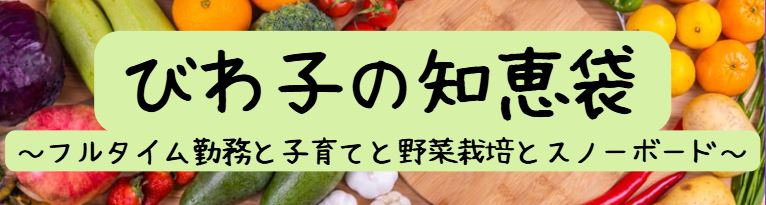




コメント