私は、産後早々にテレビの存在に疑問視をし、第一子1歳の時に、リビングからテレビを撤去しました。その後、第二子出産時期にテレビをリビングに再配置しました。育児負担が少しでも軽減されることを期待しました。しかし結果は、期待に反し、負担倍増。。。なぜ負担が増えたのか、子を観察していて感じたことをまとめています。

子育てにおいて、テレビとの付き合い方って難しいですよね。
特に、親である自分が、習慣的にテレビをあまり見ていなかったり、テレビを見ることのメリットを感じていなかったりすると、尚更、子がテレビを見ることに対し、抵抗があると思っています。
私もそのタイプの人間で、熟考の結果、幼児期の子育て中はテレビは不要という結論に達し、第一子が1歳の時にテレビをリビングから撤去しました。
当時のきっかけや理由については、以下にまとめてますので、良かったらご覧ください。
ただ、その後、第二子出産時期。
育児が少しでも楽になると期待し、一時的にテレビを再配置しました。
しかし、意に反し、育児が大変になったのでした。。。
第二子出産時、一時的にテレビをリビングに設置してみた
初めてリビングからテレビを撤去したのは、第一子1歳頃でした。
その後、第一子1歳半の頃、第二子を出産しました。
我が家は年子なこともあり、第二子妊娠期は大変でした。
第二子出産のための入院期間中は、夫初のワンオペ育児になるので、第二子出産前~産後数か月の間、テレビをリビングに一時的に配置しました。
いつまで配置するか等、あらかじめ詳細に決めていませんでした。
さて、、、結果はいかに。。。
結果としては、おもちゃで集中して遊ぶ時間が激減し、
自発的におもちゃで遊ぶというよりも親に遊んでと求めるようになり、
親の立場としてはテレビがない時期よりもはるかに手がかかりました。
【結果①】おもちゃで集中して遊ぶ時間が激減した
テレビがない時は、親が手を差し出さなくとも、おもちゃを自分で選び、一人で夢中になって遊んでいました。
飽きたら、次のおもちゃへ変え、疲れたら一人でゴロゴロしてみたりして、時々母の居場所を確認すると、ニコッと笑って、また遊びの続きに戻っていくのでした。
それが、テレビを見るようになったところ、テレビを付けていない時間帯でも、おもちゃで集中して遊ぶことが激減しました。
集中力が途切れている様子で、あれもヤダこれもヤダというかのように遊ぶおもちゃを次々と変えてみるのですが、どれにも集中できず、結局、思うように遊べず、わーんと泣くのです。
【結果②】親に遊んでと求める時間が倍増した
思うように遊べないと、私のところにやってきて、「私を楽しませて」と言わんばかりに一緒に遊んでと求めるようになりました。
テレビがない時も一緒に遊んでと求める時はありましたが、当時は、満面の笑みで近づいてきて「これで一緒に遊ぼ」と自発的に誘っているような感じでした。
当時は、誘われる回数は一日に0~3回程度で多くはなく、どちらかというと私が家事の合間に子と触れ合いたくて自分の都合や気分で余裕のある時に一緒に遊んでいることが多かったです。
そして、遊んでいる中で想定外なことが起きても、それを楽しんでいる様子がありました。
それが、テレビを置いた今や、泣きながら「私を楽しませて」と受け身な様子です。
これは何の影響なのかと様子を見ながら、求められるがままに私も一緒に遊んではみるのですが、想定外なことが起こる度にギャン泣きしていました。
【結論】テレビ無し育児よりもテレビ有り育児の方が、手がかかる。その理由は?
上述した通り、テレビがない時期は、比較的一人で集中して遊ぶ時間が長く、手がかかりませんでした。
実際、我が子と近い月齢の子がいる友人と会った際や子育て支援センターで遊ばせた際に、周囲から「一人で遊んでいる時間が長いね」とよく言われました。
それは、個人の特性だと思っていました。
しかし、テレビを配置したことで一人で集中して遊ぶ時間が人並みの長さになったので、我が家にテレビがなかったことが影響していたように感じます。
私の個人的な見解としては、テレビの子供への悪影響について一般的に言われている下記点が関係していると思っています。
- 想像力を働かせたり、自分ならこうするという思考をしなくなる
- 集中力低下、落ち着きがない、衝動的になる
我が子の場合、上記要素の影響が顕著に表れたと感じました。
我が家は、テレビをリビングに配置しても視聴時間が毎日1~2時間であり、極端に多くはありませんでしたが、元々が0時間であり、子にとっては変化が大きかったので、その分、影響が大きかったのかもしれません。
この点に関し、どの程度影響が出るのか個人差があると思いますので、これからテレビを撤去しようと考えている方は、お子様の様子の変化を観察した上で、最終的なテレビの要否を判断した方が良い気がしています。
【現在】3~4歳児育児中、育休復帰後もテレビを設置していない
第二子出産後3か月経過した頃、私の体力が回復し、二人育児の生活を立て直そうと腰を上げたタイミングで、テレビをリビングから再度撤去しました。
当時2歳近くの第一子ちゃんは、撤去直後3日程度、テレビが消えた事を不思議に思い、問いかけてきましたが、そういうもんだとすぐ慣れたようでした。
テレビを出してと怒るというよりも、なぜないのかと不思議に感じていた様子なので、親としても特別なフォローは必要ありませんでした。
(「テレビないね~」と一緒に不思議がる程度です。笑)
もしかしたら、2歳以降であれば状況が理解でき、怒るかもしれないので、テレビを撤去する時期は早い方がいいかもしれないですね。
0歳児&1歳児育児の生活が軌道に乗った後~現在、2年程経過しましたが、再度テレビをリビングに配置したいと思うことはありません。
そして、我が子が1歳児&2歳児になった時に、私は育休終了&職場復帰しましたが、その際もテレビを再度配置しませんでした。
理由は、第二子出産時の経験から、テレビを再配置してもいいことがないとわかっているからです。
そういえば夫も、テレビを再配置したいとは言いませんでしたね。
テレビを配置していないおかげか、平日の朝や夜、親が忙しく家事をこなしている間、子はおもちゃに没頭して遊んでいます。
「ねんねしようか」や「保育園行く準備しようか」と声掛けする時は、おもちゃで遊び切って満足している状態の時が多いので、スッと行動してくれます。
子にとってのメリット①:おもちゃを組み合わせて遊ぶ工夫をする
テレビがないと、その分、多くのおもちゃを用意しなくてはいけないと思われるかもしれません。
しかし意外と、家に用意するおもちゃは、普通の量で足りる気がしています。
実際、我が家はおもちゃをあまり購入していません。
じじばばからプレゼントされたおもちゃと、私が時々、セカンドストリートやメルカリなどの中古おもちゃショップで目に留まったものを購入している程度です。
おもちゃを次々と買い足さなくても、飽きたら既存のおもちゃを組み合わせて遊び始めることがよくあります。
想像力を働かせ、集中して遊んでいる時、遊びのパターンは無限大のようです。
例えば、1歳男児の遊びでは、型はめパズルの上に、実物のおもちゃを置いてみたり。

バランスボードの上にアンパンマンカーを載せてゆらゆらしてみたり。
また、第一子ちゃんは3歳からパズルにはまり、50ピースのパズルを一人で5分程度で仕上げています。
外側のピースは直線の側面があることと、外側からピースをはめていくことの2点を伝えたところ、すぐに要領を得たようでした。
ちなみに、子の好きなキャラクターのパズルを50ピース3セット、メルカリで1000円で購入しました。(おもちゃ屋さんでのパズルのバリエーションは意外と少ないので、そういう時はメルカリなどのネット中古販売サイトがとっても便利です)
最近では、平日の夕食後に姉弟2人で、30分程黙々とパズルに取り組んでいることがよくあります。
子にとってのメリット②:絵本や早寝早起きと相性が良い
一般的に、育児において絵本の読み聞かせと早寝早起きは推奨されています。
自分が育児をするまでは、幼児の読み聞かせと早寝早起きは当然と思ってましたが、いざ自分が実践するとなると大変ー。。。
ここで、これらとテレビ無し育児は相性が良いように思います。
逆に行くと、これらとテレビ有り育児は相性が悪いように思います。
テレビをリビングに配置していた時、子が自分で絵本を手に取りパラパラとページをめくる風景はなかなか見られませんでした。
子の目には、動きのあるテレビの方が絵本よりも魅力的に映るからでしょう。
また、睡眠前1時間以内のテレビ視聴は寝つきの悪さにつながると一般的に言われていますが、
私の感覚では、子どもの場合、2時間以内のテレビ視聴すら寝つきに影響があるように感じます。
例えば、18時過ぎまでテレビを見ていて、20時に寝かしつけを始めた場合、子が寝入るまでに大幅に時間を要し、寝かしつけに時間がかかるのです。
我が子の場合、寝かしつけ時間は、テレビがない時は15~45分程度、テレビがある時は1~2時間程度でした。
当時、寝かしつけにやたら時間がかかる原因は、昼寝が長すぎることにあると思い込んでいましたが、今思えば、テレビを見ていた時期と寝かしつけに悩んでいた時期はもろ被りしています。
そして、テレビを再度撤去した途端、寝かしつけの悩みもなくなりました。
ご経験ある方は共感いただけるかと思いますが、寝かしつけに1~2時間要することは、かな―――りストレスです(-_-;)
しかも、夕方は一日の疲れが出てきて意志力が落ちるので、子はだらだらとテレビを見たがります。
それを17:30までと制約を持たせると、もちろん子はぐずりますし、実現は難しいです。
結果論での感想ですが、子にテレビを毎日1~2時間見せ、寝かしつけに1~2時間かけることを毎日ストレス感じながら繰り返す日々は、効率が悪いことを薄々自覚していて、ぼんやりと虚無感に襲われていました。
親にとってのメリット:頭のメモリを浪費しない
育児をしていると、頭の中で無数の小さなTODOを常に考えている事が多いと思います。
例えば、
- 保育園のおしりふきが終わったみたいだから、保育園バッグに補充しなきゃ
- 〇日は定期健診だから、定期健診の後に登園となると、〇時に家を出なきゃ
- 定期健診の用紙はいつ記入しようか
- 今日の夕飯は、昨日の残りと、〇を焼いて・・・
- あ、夕飯のデザートの果物がないぞ
- あ、うんち漏れちゃった。とりあえず予洗いしたけど、いつ洗濯機を回そうか etc.
3分程度で上記のような類を考え、仕事もしていれば更に仕事の事。
そして、場合によっては数分おきに子供に話しかけられる・・・
「ママ、おしっこ行くよー」「早くご飯食べたいな~」「今日、ポポちゃんがね~」
聖徳太子じゃないんだから、同時進行で3つ以上をこなすことは難しいです。
更にここにテレビの音となると、ニュースでも頭の中に入ってこないし、もはや雑音のように聞こえる・・・
しかし、気になるからちょっとアンテナは立てておく、それにより更に注意力散漫になるし、頭のメモリを浪費する。
結局、聞き流しているテレビから得られる情報ってわずかどころか皆無に近い気がします。
【今後】視聴時間を自分で管理できるようになったら、TV設置するかも
テレビを配置すれば、映像により子が多くの情報をイメージとして得ることができ、会話や創造の幅が広がるということは認識しています。
ただ、上記メリット3点が失われると思うと、現時点では、就学前~小学校低学年頃までは不要かなと思ってます。
少なくとも、〇時~〇時まで見る等、自分でテレビを見る時間を管理、制御できるまでは、不要かな。
テレビから得られるメリットの方が大きいと感じたタイミングで、テレビを設定したいと考えてます。
最後まで読んでくれてありがとう☀
一緒に頑張りましょう😊
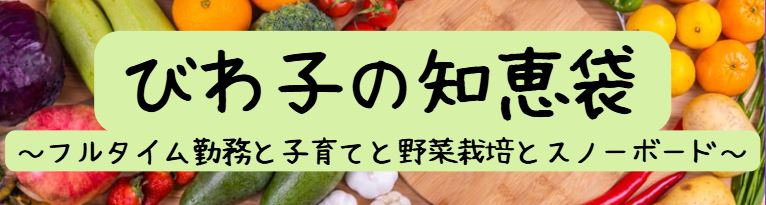




コメント