ブラウント病治療の為に、我が子は2際から装具を付け始めました。イヤイヤ期最盛期の2歳児に装具を付けることはとっても大変でしたが、試行錯誤の結果、毎日装着してくれるようになりました。本記事では、当時、実践した対策についてまとめてますので、これから2歳児の装具治療を始めるご両親等のご参考になれば幸いです。
※下記写真は、お風呂から上がった後に突如自分から装着し始めた時の様子。
ちなみに左右逆です(もっとO脚になっちゃう)。

ブラウント病疑いと診断された娘は、2歳2ヶ月から装具治療を始めました。
つまり、2歳2ヶ月から、日中の活動時間に装具を装着する生活が始まりました。
当時、娘はイヤイヤ期最盛期でした。
何でもイヤイヤと言う。
さすがにこれは嫌ではないだろうとこちらが思っていても、イヤイヤという。
そんな子にとって、装具装着はイヤイヤの格好の対象であり、装着してもらうことは想像よりも遙かに大変でした。
そこで、検討を重ね、自分や子と向き合い、試行錯誤をして、最終的には毎日自分で装着してくれるようになりました。
本記事は、その試行錯誤の際に実践した対策についてまとめています。
初めての装着から習慣化までの慣らしスケジュール
対策の前に、どのようなスケジュールで装着を慣らしていったのかについて記します。
医師の先生からは

装具はある程度重さがある為、初日から一日中装着することは体力面での負担が大きいです。少しずつ時間をかけて慣らして行きましょう。
とアドバイスを頂きました。
装着に関するアドバイスや、基本事項、ズボン等の衣服、オムツ替えなどについては、以下にまとめてますので、良かったらご覧ください。
先生のアドバイスを踏まえ、2週間程度かけて以下のステップを経て、装着を習慣化させました。
| スケジュール | 時間帯 | 時間の目安 |
| Step1 | 9:00~11:00 | 午前遊び~昼食前まで |
| Step2 | 9:00~12:30 | 午前遊び~昼食後まで |
| Step3 | 9:00~15:00 | 午前遊び~昼寝後まで |
| Step4 | 9:00~17:00 | 午前遊び~お風呂まで |
上記ステップは、慣らし保育スケジュールのようなイメージです。
各stepの日数は子どもの反応を見つつ短くしたり長くしたりしました。
開始時間の9:00は固定ではなく、8:00~10:00の間に機嫌を見ながら付けていました。
付けるタイミングはできるだけ子に合わられるよう、8:00~10:00の幅を取り、時間的余裕を持ちました。
8:00頃から装着しようかと声をかけていき、断られたら、「OK。また後でね」と下がる。
15分後にまた声をかけて、断られたらまた一歩下がる。その繰り返しです。
次第に、装具を付けるとお出かけできると本人が認識し、自分が出かけたいタイミングで装具を履いて準備するようになりました。
しかし、出かけるタイミングで装着に気分が乗らない場合もあります。
そのような場合は、上記2週間の間に限り、午前中の装着は諦めて、お昼寝前などに装着する時もありました。
このようにステップを経て習慣化までもっていきましたが、実は、step1を2日ほど行った後に、10日間程付けずにお休みし、その後上記スケジュールを再開しました。
10日間ほど付けなかった理由は、自分の中で作戦会議をしていた為です。
というのも、step1の2日間が、全然、一筋縄では行かなかったのです。
羽交い締めにして装着させれば装着したでしょうが、それは避けたかったので、対策を練りました。
その後、練った対策を実践しながら2週間かけて慣らして行き、習慣化させることができました。
習慣化後もイヤイヤ期最盛期の間は定期的に装着を嫌がることが多々ありましたが、イヤイヤ期後半にさしかかると、自分で装着してくれることが増え、イヤイヤ期が終わると、毎日自分で装着するようになりました。
では本題に。
10日間休んだ際に私が考え、そして実践していった対策について、一つずつ説明します。
【対策①】子どもと向き合う前に自分と向かう ~納得と覚悟~
完成したばかりの装具を試しに2日ほど娘に装着させようと試みた時に、悟りました。

あ・・・これ、中途半端な気持ちで始められないやつだ。
最初、娘は興味本位で装具を触っていましたが、履くと重いし動きにくいということが分かると、想像以上に付けてくれません。
本当に全然。。。
その時は、装着してくれる未来が想像できないほどに、「これ、どうしたらいいんだ?」とお手上げ状態でした。
そして、考えた結果、選択肢は以下2つかなと。
- 力技で無理矢理装着させる
- 心理的に訴えて、装着したい気持ちに持って行く
ただ、1.の力技案は、早々に却下しました。
装着に限らず、イヤイヤ期の子に無理強いすると、その後、不機嫌な時間が長引いたり、大きくイヤイヤされたりするので、後が大変。
そして無理強いする時に、こちらの力が必要なので、私自身が疲れるし、心が痛いし、感情的になるし、娘は泣くし、それにつられて弟も泣くし、二重の泣き声に自分が焦るし、その後の二人へのフォローに時間を要すし。
お互いにとって、ろくな事がありません。
となると、2.の心理的に訴える案。
娘の機嫌を取りながら、根気よく誘導していくしかありません。
自分の根気を継続する為には、装着よりも、まずは下記観点で自分と向き合うことが必要だと考えました。
上記3点を、自分の中で腹落ちするまで考えました。
特に一点目については、自分が少しでも装具治療の効果に疑いを感じていたら、自分が継続できないし、娘に見透かされ、娘も治療に疑いを感じ、いつまでのイヤイヤすると思うので、自分に腹落ちさせる必要があると感じました。
そして実際、装具装着を開始し、ただせさえ忙しい年子育児の中で装具治療を諦めたくなる場面は何度も訪れましたが、上記3点に納得していたおかげで、自分がぶれずに治療継続に向け行動できました。
余談ですが、他方で夫は、最初の1年は土日の装着にしか関与していなかったからか、私のように強制的に自分と向き合わざるをえない状況にはならず、未だに装具治療に疑いを持っているようです。
結局、装具治療の効果は結果論なので、中途半端な気持ちで治療していれば、矯正ベルトを強く締めなくなり、効果も中途半端になると思います。
なお、矯正ベルトの締め具合と効果(骨の角度)の関係についての体験談は以下にまとめてますので、良かったらどうぞご覧ください。
上記記事に記載しておりますが、しっかり矯正ベルトを締めて毎日装着していれば、治療効果は確実にありました。
【対策②】装着を無理強いすると逆効果。後で大爆発する
上記章で少し触れましたが、装着に限らずイヤイヤ期の子に何かを無理強いすると、その後、不機嫌な時間が長引いたり、大きくイヤイヤされたりするので、後が大変。ろくな事がありません。
しかし、時には、出発時間が差し迫っていて、無理矢理装着させねばならない場面があります。
無理矢理装着させた日は決まって、例えば夕方などに他の事でイヤイヤが始まった際に、堪忍袋の緒が切れたように大爆発します。
何度かそのような経験がありますが、私が無理強いしたことに起因していると心当たりがあるので、その度に大反省。懺悔のような気持ちでその大爆発に付き合う事になります。
大反省するポイントは、無理強いさせなきゃいけなくなるようなスケジュールを組まないこと。
具体的には、以下です。
装具装着に関して、無理強いさせられたと悪い印象を残さないことが、自ら率先して装着してくれることへの近道だと考えました。
【対策③】説明、説得、そして交渉
娘が2歳2ヶ月の頃に話す言葉は、いわゆる宇宙語が多く、話したとしても二語文程度、文章は話しませんでした。
しかし、相手の話を真剣に聞き、くみ取る力はある程度あるように見えました。
どこまで理解しているのか分からないですが、まずは説明しました。

足が曲がってるので真っ直ぐにする為に装具をはこう。
足が真っ直ぐになれば、転ぶ事が減るよ。
次に共感しながら説得。

重いよね。きついよね。
装具を履けば足が真っ直ぐになって走りやすくもなるよ。
履いてくれたらとっても嬉しいな。
そして、時には抱きしめながら、交渉。

そうだね、やだよね。
気持ち、分かるよ。
そしたら、装具付けてお出かけして遊びに行こっか!
どうかな?
なぜ装着しないといけないのか理解してもらう為に、治療開始数日間は特に「説明」が必要だと思います。
最初は、交渉までの3段階を毎日行ってましたが、次第に、説明だけで装着してくれる日が増えていきました。
言葉での訴えがその子にどの程度響くかについて、性格面での個人差が大きいかとは思いますが、我が娘は人の表情や話をじっと観察している様子がよく見られたので、言葉での説明に重きをおいて実践しました。
このように言うのは簡単ですが、実践するには本当に忍耐が必要でした。
親子関係が問われているように感じることもありました。
私は模索しながら実践していたので、親子関係にヒビが入りそうなギリギリを攻めているような状態になっていた時期もあります。
そんな時期を経て考えた事は、どうせ理解できないだろうと子どもへの説明をはしょるのではなく、一人の人間として接し、行動へ繋げることが、結果的に自ら装着してくれることに繋がると考えました。
【対策④】とことん気をそらす。何かに夢中になっている時にしれっと装着させる
上記説明→説得→交渉を毎日行うと、何度も聞いていることなので子どもの方も耳たこ状態になり、飽きてきます。
これ以上説明は不要で、でも今日は自分から装着してくれそうにない場合は、全神経を装具に向けることは避け、手遊びしたり、おしゃべりしたり、絵本を読んだりしながら装具を付けるようにしました。
本人も装具を付けなきゃ行けないことは理解していて、でもなんだか気乗りしないといった場面で有効です。
ちなみに、YouTubeを見せながら履かせたこともあります。
日常的にYouTube視聴をOKとされているご家庭であれば、この方法は支障がないのかもしれません。
私はできるだけ子にテレビや動画を見せたくないという考えなので、装具装着の習慣化とともに、YouTube視聴も習慣化してしまったので、その点で私としては大失敗でした。
YouTubeがなきゃ装具を付けないと嫌がるようになり、YouTubeがなくても装具を付けるよう戻すまでとても労力がかかりました。
【対策⑤】常に自分の機嫌を取っておく
5つ目、最後の対策ですが、意外とこれが一番大切で効果大かもしれません。
装具に限らずですが、イヤイヤを発動され、例えば予定通りに動けなかったりすると、こちらもイライラします。
イライラを貯めておくと、子どものイライラに付き合えなくなってきて、悪循環にはまっていきます。
自分がイライラしているなと感知したら、そのイライラをその日のうちに解消する為に、甘やかすポイントを日常の各所に用意しておくことです。
例えば、私が自分を甘やかす手段は以下です。
- キッズコーナーが豊富な飲食店で外食(近場に3~5軒ほど見つけました)
- お昼はおにぎりのみ、離乳食はレトルト。
- 公園へ行く途中でスタバで飲み物をテイクアウトする
上記何回か実践していくと、その場に行ったり、行く予定を考えるだけで、イライラスイッチがオフになり、リラックス状態になりました。
装具慣らしスケジュール期間中は、上記甘やかしを毎日行う位に自分に余裕を作って、子どものイライラに備えておくと、悪循環にはまらなくて済むかと思います。
最後に
装具治療を開始し始め、上記対策を試行錯誤していた当時、他の人はどうやっているんだろうと、聞きたくて仕方ありませんでした。
しかし、通院している中で、私は、同じくブラント病装具治療をしている他の患者さんに出会った事はなく、対面で会話したこともありません。
病院においてそのような交流の場はありませんし、個人情報でしょうから、病院に聞くこともできませんでした。
その為、本ブログではブラント病治療についてあえて詳細に、些細なことでも記事にまとめることにしました。
本記事にまとめた対策は、我が子を観察して有効だと考えた対策ですので、万人受けしないと思います。
使えそうな対策を取捨選択して試し、お子様の反応を見て、継続するか最終的に決定されるのが良いかと思います。
あくまでも体験談であり、一例ですが、1人でも参考になったと思われる方がいらっしゃれば幸いです。
今日も素敵な一日になりますように☀
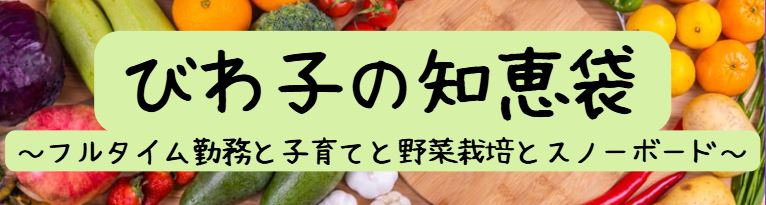





コメント