我が子は、第一子女、第二子男の年子です。本記事では、出産前に想定していた年子の良い点&大変な点と、その現実について、記載してます。結果論ですが、現時点では、親子双方にとって、年子で良かったと思ってます。第二子産後1年間は確かに大変でしたが、それ以降は、年子であることが日々プラスに働いている面の方が多いと感じています。

出産や育児において、事前に想像していなかった事が多数発生する、ということは、世のママが経験していることかと思います。
私の出産の想定外と言えば、
「産まれたばかりの赤ちゃんがこんなに寝ないと思わなかった」
「授乳がこんなに痛いものだと思わなかった」
「出産時の傷の痛みが、産後しばらく続くとは思わなかった」
などです。
では、年子育児(1歳差の兄弟)については、予想と現実にどんなギャップがあったのでしょうか。
その点について、以降、実体験を中心に記載します。
一般的な良い点と大変な点
実体験を記載する前に、年子育児について、一般的に言われている良い点と大変な点について、触れます。
一般的な内容は以下の通りです。私はこれらを覚悟はしていました。
※以下、便宜上、上の子を「第一子」、下の子を「第二子」と表現してます。
第二子以降を上の子として年子を出産される/された方は、ご自身の状況に読み替えてください。
◆良い点◆
◆大変な点◆
想定外だが、結果的に良い方向に進んだこと
では、本題に。
上述した一般的に言われている良い点を年子出産前に想定しておりましたが、予想すらしてなかったが良かった、予想に反して良かった、予想以上に良かったことは主に3つありました。
以下、順に記載していきます。
第一子が「女の子」の為、年子育児が軌道に乗りやすかった
これは、予想すらしてなかったが良かった点です。
性別でひとくくりに考えるのは良くないと思いますが、正直なところ、
第一子が「男の子」よりも「女の子」の方が、年子育児による親の負担度が比較的少ないと感じてます。
我が子は第一子が「女の子」、第二子が「男の子」ですが、仮に第一子と第二子の性別が逆に産まれてきた場合、日々のお世話に今の倍は手間がかかった気がします。
理由は、各性別の特性による影響です。
一般的な性別による乳幼児の特性は以下の通りです。
◆女の子◆
・周囲の状況をよく観察しており、変化に敏感
・相手の感情を理解、共感することが得意
・感じた事や見たことを表現しようと、おしゃべりが好き
・好奇心旺盛、自立心が強い為、一人遊びが得意
・お手伝いや年下の子の世話が好き
◆男の子◆
・夢中になっていると周囲が目に入らない
・「動く」ものに興味があり、周りに意識が向きやすく、気が散りやすい
・空間認知能力が高い
・「聞く」力が弱い
出産により新入りの赤ちゃんが急に家に登場した時、上記女の子の特性が後押しし、私は第一子に何度も助けられました。
具体的には、第一子は第二子を自分がお世話する対象として迎え入れ、必死な私の感情を瞬時に察知し、第二子の様子を私に伝えようとし盛んにおしゃべりしてくれました。
また、周囲が忙しない時は、我関せずと一人遊びに没頭していました。
これが仮に第一子が男の子の場合、経験はないので想像ではありますが、赤ちゃんを「お世話する対象」というよりも「動くもの」として認識し、赴くままに、どんな反応があるかつついたり触ってみる気がします。
周囲の言葉は耳に入ってこないので、やり続けた結果、赤ちゃんが不快に感じ、意図せず泣かせてしまう事があるでしょう。
現在、娘は4歳ですが、私が第二子の対応に困っていると、
「〇君はxxxしたいんだと思う」「xxxしてあげればいいよ」
とアドバイスくれたり、必要なものを持ってきてくれたりします。
第二子がうんちをし始めた時点で、その匂いを察知して私が何も言わずとも、新しいオムツとお尻拭きを持ってきて、「オムツ替えて上げて」と言ってきたりします。
個人的な性格も影響しているのかもしれませんが、性別による特性が背中を後押ししてくれていると感じています。
第一子が最近できるようになったことを第二子に教えてくれる
私は第二子出産以降、余裕がなく、第一子のトイトレやお箸の使い方などを率先して教えられず、第一子のオムツが外れる時期やお箸が使えるようになる時期は遅くなりました。
その為、第一子がそれらをできるようになった時期と、第二子がそれらに興味を持ち始めてきた時期が被り、第一子は自分ができるようになったことを教え、第二子は前のめりに覚えようとしてくれています。
親の出る幕はほぼなく、弟は姉の様子を見て、ぐんぐん吸収していっています。
最近では、第一子のトイトレが完了し、自分でパンツを選び、履いて、トイレに行ってますが、第一子がトイレに行くときは必ず第二子も付いていき、ドアの前でじっと様子をうかがっています。
おもちゃ遊びの時も同様で、姉が編み出した遊びを、弟は満面の笑みで真似しています。
余談ですが、我が家にはテレビを配置していません。
その影響もあってか、特に姉は、既存のおもちゃを組み合わせたり、本来のおもちゃの用途とは異なる用途でジャンルを変えて空想の世界で遊んだり等、私が想像もできないような遊びを編み出し、夢中で遊んでいます。
それを弟が真似し、工夫をし、更に新たな遊びを編み出しています。
テレビを配置していないことについては、下記記事にまとめてますので、良かったらご参照ください。
ずっと一緒に遊んでいる
上述した、姉が弟に遊びを教えてくれることに伴い、我が家の場合、各自で別々の遊びをしている時間よりも、一緒に遊んでいる時間の方が圧倒的に多いです。
姉は教えることを、弟は教えてもらうことをお互い楽しんでおり、その延長で、一緒に遊んでいます。
一緒に遊ぶ割合について、年子出産前は、一緒に遊ぶ時間は半分程度で、残り半分は別々に遊んでいるだろうと想像してました。
現実は、8~9割方、一緒に遊んでいます。
それだけ一緒に遊んでいると、姉4歳、弟2歳半の現在、30分ごとに1回ペースで小さな喧嘩をしますが、親が仲裁に入る間もなく気持ちを切替え、遊びを再開している様子がよく見られます。
特に、平日の保育園帰宅後、私が家事を片付けている時間帯は、姉が「一緒に遊ぼ―!」と声をかけて遊んでいます。
しかし、姉の気分次第で、時に一人でゴロゴロしたい時もあるようで、そんな時は、お声がかからず、弟はがっかり。
弟は、姉や私の周りをうろうろしたり、ちょっかいだして遊んでもらおうとします。
逆もしかりで、弟が真剣に本を読んでいる時は、その横に姉が寝転がり、本を読み終わるのを待っています。
そのような様子から、お互いに一緒に遊ぶことを楽しみにしていると思ってます。
また、姉は家にある本は繰り返し読んで内容をほぼ覚えているので、4歳時点でまだ字を読めませんが、姉が弟に読み聞かせをしていることがよくあります。
ここまで一緒に遊んでくれるとは想像していなかったこともあり、私としては家事に集中できて有り難いとともに、可愛らしい風景だなと眺めてます。
想定以上に、大変だったこと
それでは、予想に反して大変だったことについて、記載していきます。
第二子妊娠のつわり期と、第二子産後三ヶ月間は、過酷。
第二子妊娠のつわり期と、第二子産後三ヶ月は、自分の記憶から抹消したいくらいに、辛い時期でした。(既にほぼ末梢したので、記憶があやふやです笑)
まず、第二子妊娠期のつわり期については、私の場合、つわりが第一子よりも第二子の方が重かったことが一つ目の予想外でした。
第一子のつわりくらいの重さであれば、つわり中も第一子の1歳児育児を乗り越えられると想像していましたが、経験したことのない吐き気の日々に、第二子妊娠期のつわり期は、一日一日を生きるだけで必死でした。
そんな中でも育休中の私は日中も1歳児育児をしなければならず、公園遊びや買い物などで出かけ、ゆっくり休息していなかったので、更につわりの症状が重くなったのかもしれません。
次に、第二子産後三ヶ月間。
この時期が大変になった原因は、いわゆる「夫育て」を私がしてこなかったことに起因している気がします。
第一子出産以降ずっと私は育休中だったこともあり、第二子出産入院の時期に夫は初めて丸一日以上、第一子と過ごしました。しかも連続6日。
第二子出産退院日には、夫は疲弊してました。
しかし、第二子出産退院日は、私からするとむしろこの日から、夫には本腰入れて育児に参戦して欲しかった。
しかし、私の入院中、自分(夫)は頑張ったので、後はよろしくと言った様子でした。
私は、産後ボロボロの体で第一子&第二子の年子育児を必死にやっており、子一人の世話なら非常に楽だと感じているのに、片や夫は子一人で手いっぱい。
そんな日々が続き、夫に対し私が強い嫌悪感を感じ、夫はそれに対し、「こんなに頑張っているのに」という不満を募らせていました。
最終的に、私は夫育てよりも先に、一時保育や産後ケアなどの外部の助けを借りて、この時期を乗り越えました。
育休から職場復帰した今になってやっと、家事育児分担を見直し、夫育てをしているところです。
この「夫育て」という言葉を、個人的には私は嫌いなので(育てられるのではなく、自分で育ってくれと思う)、してこなかった(夫を育ててこなかった)のですが、現実問題、夫が妻のフォローなく家事育児をこなせる状態で第二子出産に挑まないと、夫婦仲は破滅の一途だと経験しました。
また、「女の人は妊娠期から母になり、男の人は産まれてから父になる」とはよく言われますが、私はその認識が甘く、第二子出産直後から私が夫に過度の期待をしてしまったのかもしれません。
なかなかね、難しいですね。。
父になる心の準備をする余裕を夫に与えられなかった
以下、完全に私の主観ですので、悪い気分にさせたらスミマセン。
上述した、「女の人は妊娠期から母になり、男の人は産まれてから父になる」と言う言葉から表されている通り、男の人の場合、妊娠期間中から父の自覚(?)を醸成するのは難しいと感じています。
それは、自分が妊娠しておらず、妊娠期に身体的な大きな変化が生じてないことが最大の要因でしょう。
妊娠期間中から父の自覚をもてている人は、妊娠中の妻とのやりとりを通じ、妻を心身共にサポートをすることで、その自覚が醸成されていると想像してます。
心身のサポートとは例えば、
妻と同様にお酒をやめてみたり、
妊娠中に食べない方がよいとされている食材を認識し、細心の注意を払ったり、
妊娠期のホルモンバランスによる心情を理解しようと努めたり
嘔吐している時に背中をさすったり。
こう書いてみると、女性からするとできて当然の内容に見えますが、実践している男の人はとても少ない気がします。
しかし、上記のような対応をできている男の人は、妊娠期から常に妊娠を意識できているので、出産への心理的準備ができているのだと思います。
逆に言うと、上記のような対応をできていない多数の男の人の場合、日常に突然、出産というイベントが登場するので、心の準備ができておらず、出産してから心がついてこず、焦るのかなと想像してます。
まさに私の夫がそうでした。
そんな夫に対し、私はどう接すれば良かったのでしょうか。
理想は、夫自ら、上記心身のサポートをして、夫婦で妊娠を乗り越えて行ければいいのでしょうが、そこに意識が向いていない夫に対し、妻はどう動けばいいのでしょうか。
この辺りは未だに私の中で答えが見つかっておりません。
結局、第二子2歳までは、夫は第一子の対応で手一杯で、第二子がぞんざいに扱われ、二人を同時に任せることはできませんでした。
第二子2歳以降は、第二子と父のみの時間を多く作り、徐々に慣していったところ、第二子の動きや反応に応じた対応ができるようになり、子二人を同時に任せることができました。
そう考えると、二児の父になるのに、丸2年かかりました。
第二子出産のために第一子が入園した保育園が著しく合わなかった
第二子妊娠時、私はまだ第一子育休中で、第一子はまだ保育園に入所しておりませんでした。
ただ、第二子妊娠臨月~第二子新生児期は特に自分の身体が万全ではない点と、第一子と第二子の二人を一人で育児できるか自信がない点が理由で、たまたま保育園の方に空きがあったこともあり、出産を理由に第一子を一時的に保育園に入所させました。
しかし、私も娘もなかなかその園になじめませんでした。
今思えば、単に相性が合わなかったのだと思います。
ただ当時は、保育園というものに初めて通う上に、保活の経験もなかったので、その園に合わせてこちらが動こうと考えてました。
その為、日々の気苦労が多くありました。
気苦労して登園するくらいなら、潔く退所すれば良かったと今では反省してます。
冷静に第一子の様子と自分のストレス具合を考慮し、退所の判断を取れば、もっと早くから二児の自宅保育が軌道に乗った気がします。
ただ、朝晩の区別がついていない新生時期は、自分が夜にまとまって寝れていないので、この「冷静な判断」がとっても難しいです。
【結論】年子出産して良かったと心から感じる
結果的に良かったことや大変だったことはありますが、総じて考えるとプラマイゼロ~プラスで、想像してたより極端に大変だったというはありませんでした。
現時点で我が子はまだ幼児であり、育児真っ最中なので、今後、何が起こるかわかりませんが、第二子が2歳半の現時点では、年子で良かったと思ってます。
特に、良かった点でも記載した「一緒に遊ぶことが多い」については、親が楽、というのもありますが、それ以上に、見ていて微笑ましいです。
また、姉の方が年上なので知恵はついていますが、弟の方が力は強いので、喧嘩で圧倒的に姉が強いということはなく、どっこいどっこい。
片方が負かされてばかりという事態にはなっていません。
その為、小さな喧嘩が何回も起こりますが、どちらかが圧勝するような喧嘩は起こりにくい為、親が仲裁するまでもなく、自分達で解決できているのかなと思います。
また、姉弟間でお互いに甘えたり、心配したり、優しく接する場面もあります。
どちらかがお腹がいたかったり、機嫌が悪かったり、転んで怪我したときなどです。
2歳以上歳が離れていると、どうしても上下関係が確立しやすいですが、年子は上下関係は目立たないので、そういった意味で、対等な関係の兄弟がいるというのは、今後心強い存在になるかなと期待も含めて考えてます。
最後まで読んでくれてありがとう。
今日も素敵な一日になりますように☀
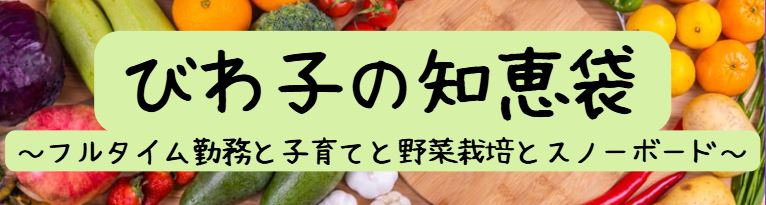




コメント