子がテレビを見続けて困る、それにより母である自分が罪悪感を感じる、という悩みを抜本的に解消する為に、我が家はテレビをリビングから撤去しました。テレビはリビングにあって当然と考えがちですが、子育てに関しては必需品ではないと考えてます。私以外にも子にテレビを見せていない子育て家庭はたまにいますが、どんな思考回路で見せなくなったのか、ご興味ございましたらご覧ください。

当然のように、テレビがリビングに置いてある現代。
テレビは手軽に情報収集できますし、そのメリットは計り知れません。
ただ、テレビが生活における必需品か?と考えると、そうではないと思います。
実際、我が家にはテレビはありませんが、生活が十分成り立ってます。
ただ、今はテレビのない生活に慣れていますが、ここまで来るのに、多くの自問自答と葛藤を繰り返しました。
本記事では、テレビのメリットを重々承知した上で、幼児期の子育てには必要ないと私が結論づいた背景や理由についてまとめています。
これから出産する方や、子育て中でテレビとの付き合い方に悩んでいる方、子どもへの声掛けにモヤモヤしてる方の参考になれば幸いです。
【きっかけ】産後早々、テレビの存在に疑問視し始めた
第一子出産後、自分がテレビを見なくなった
産後、多くの子が1歳前後まで、1年前後の夜泣きがありますよね。
夜泣きがあると、親は夜中にほとんど寝れません。
その為、自分自身の睡眠時間が確保出来ず、睡眠不足に悩まされます。
我が子が0歳児の時も、私はひたすら寝不足に悩まされていました。
睡眠時間を確保する為に、子の昼寝時に一緒に寝ようと努めていました。
そんな時、直前までテレビを見ていたりすると、眠いのにすぐに寝付けず、イライラする訳です。
そして、子のお世話に追われている為、そもそもテレビを見る時間すらない訳です。
ある日、無理にテレビを付ける必要はないと感じ、一日に一回もテレビを付けない日が生じ、その日を境に、テレビを付けない日が続きました。
そして、テレビを付けない事が当たり前となり、テレビは埃をかぶっていきました。
テレビを付けなくてもテレビ周辺の埃を掃除する必要はあり、使ってもない家電のためにこの掃除って必要?という疑問が沸々と湧いていました。
夫が土日にテレビを見る日々。ただ、テレビを消すと、子が泣く
それでも、リビングにテレビを置き続け、夫が居る土日のみテレビをつけていました。
当時、私は育休中で、平日のテレビ視聴時間は0時間、土日は数時間という日が続きました。
そんな中、感じたことは、テレビを付けるタイミングも消すタイミングも大人の都合。
そして、テレビを消すと子は泣く。
そりゃ泣きますよね、見ていた映像が突然消えたんだもん。
言い換えると、親の都合でテレビを消されて子が泣いているという状態。
更には、我が家は平日はワンオペ、土日はツーオペ。
土日は手が足りているので、テレビに育児をしてもらう必要もなく、しかも親の都合で泣かせている、
この泣いている時間って子の為になっている?
自分は何やってんだろうか?何がしたいのだろうか?・・・と違和感を感じるようになりました。
検診時、テレビ視聴時間が長くないか毎回注意される
自治体主催の検診で
3か月検診、9ヶ月検診、1歳半検診、2歳検診、3歳検診、、、、と3歳までに定期的に検診があります。
どの検診でも、毎日のテレビ視聴時間について問われる事に気がつきました。
気がついた時は、2回目の検診でしたが、3歳検診までずっと問われ続けるんだろうなと容易に想像が付きました。
そして、0歳よりも1歳、1歳よりも2歳と、テレビ視聴時間の注意の度合いが厳しくなってくことに後々になって気が付きました。
子が大きくなるにつれて、テレビを見たがり、視聴時間が増え、それに伴い、検診での注意も厳しくなるのでしょうね。
既にテレビに対し後ろ向きの私は、
検診で注意されるようなテレビをわざわざ子に見せる必要ある?
ないよな~
と自問自答してました。
この時には既に、子にテレビを見せる必要がないと自分の中で結論づいていた気がします。
以上3点のきっかけにより、テレビをリビングから撤去する選択を考え始めました。
ただ、上記3点はあくまでもきっかけに過ぎず、決定的な理由となったことは、テレビに関する自分から子への声がけでした。
【理由】自分の声がけの矛盾にモヤモヤしていた
「〇時になったら or この番組が終わったら、テレビ消すよ~」を0歳児が理解できるか
土日に夫がテレビを付け、夫自身は子の視聴時間に興味がないようだったので、結局は私がテレビを消す役割を担っていました。
子がテレビを見ている時に急にテレビを消すことに抵抗があった私は、テレビを消す数分前に
「〇時になったら or この番組が終わったら、テレビ消すよ~」
といったテレビを消す予告を行うようになりました。
ただ、時間感覚が着くのは3歳程度と言われているので、1歳前後の子がそんな予告を理解できる訳がありません。
子が理解出来そうもない言葉を私が発し、もちろん理解されず、結局泣く、、、何がしたくて私はテレビを付けたのだろうかとやはり感じました。
この違和感を感じてまで、テレビを見させ続ける動機が見当たりませんでした。
「(画面から)離れて見なさい」を0歳児が理解できるか
子どもって、テレビに触れるくらいの距離まで近づいて見ますよね。
画面に映っているものは何なのか、触れたいんでしょうね。
我が子の場合、どんなに注意しても、テレビに近づいていきました。
私は極度の近視の為、テレビに近づいて見る子の様子が気になってしかたありません。
テレビに近づきにくいよう、テレビの前に滑り台を置いた時もありますが、その滑り台の合間をぬって、結局は、テレビの目の前で見ていました。
「テレビから離れて見る」という私の要求に答えられる年齢には達していなかったのでしょう。
理解できそうもない言葉を自分が発している事への矛盾やモヤモヤを感じました。
例えるならば、人参を目の前にぶら下げて、食べるなと言っているくらい(笑)、自分の発言に無理があるように感じたのです。
テレビは、子がぐずった時に黙らせるツール?
前述したとおり、我が家でテレビをつけるのは土日、つける人は夫でした。
テレビをつけるタイミングは、子が不機嫌だったり、ぐずったりしている時がほとんどでした。
親の感情としては「めんどくさいな」と思っているような時です。
個人的な意見ではありますが、そのタイミングが、私はとっても嫌でした。
平日の昼間、夫が不在の間に子が不機嫌になった場合、私は抱っこしてあやしたり、外の空気を吸いに行ったり、絵本を見せたりして、どうにかご機嫌になるよう苦戦していました。
それをいとも簡単にリモコン一つで解決してしまう夫を見て、子の気持ちを受け止めることを放棄していたように感じたのです。
テレビがある限り、彼は子の不条理な要求から逃げ続けるように、当時の自分の目に映りました。
そして、夫は、子がぐずる度にテレビを付けて、膝の上に子を座らせ、一緒にテレビを見るのでした。
この光景を見て、「テレビが夫の育児成長を妨げている」と私は解釈しました。
子が負の感情を訴えた時、テレビではなく親が受け止めてあげたい
話が脱線しますが、大切なことだと思うので、あえて触れます。
例えば、兄弟喧嘩の時、思うようにおもちゃで遊べなかった時、気分が乗らなかった時などなど、
子が突然泣いて、負の感情を親に訴えてくる時があります。
そんな時、子の感情を受け止めて、抱きしめて、落ち着くまでそばにいてあげたいと私は思い、実践してきました。
しかし、現実問題として、それを実践できないほどに時間的余裕がない時もあります。
そういった時、一時的にテレビに頼る場面があっても致し方ないと思ってます。
だって他の場面で頑張っているんだもん。
テレビを見せている時間の何倍もの時間を、子と向き合って過ごしているんだもん。
その為、他のママさんたちがテレビを沢山見せていたとしても、それほどまでに大変なんだと思い、いけないことだとは感じません。
しかし、例えば朝夕しか子と顔を合わせないようなパートナーが、何の迷いもなくテレビに育児させる選択をとることはちょっと違う、、、いや、かなーり違うなと思ってます。
短時間しか子と過ごす時間がないなら尚更、不機嫌な時の子と正面から向き合ってほしいと考えています。
【最大の壁】変化を受入れられない「夫」
話は戻りまして、上記きっかけや理由から、我が家はリビングからテレビを撤去しました。
ちょうど引っ越しのタイミングも重なり、引っ越し先ではテレビを置きたくない旨をどさくさに紛れて私は夫に伝え、快諾を得ました。
夫は、普段、育児にあまり関われていない負い目があるのか、深く考えずに快諾したようです。
そして、引っ越しのバタバタを終え、テレビのない生活が始まりました。
子が泣くと真っ先にテレビをつけていた夫、そんな夫からすると、テレビがないということは、泣いてる子をあやさなければならず、一手間も二手間も増えるわけです。
今までは0歳の子がいる家で携帯いじりながらダラダラ出来ていたけど、それが叶わず、しょっちゅう、子の「かまってー」に突撃されることになります。
私としては、子の負の感情を夫が受け止める機会が出来たので、ニッコリです。
片や、夫は、嫌で仕方ないようでした。
しかも、夫は常にBGM代わりにテレビをつけていたいタイプの人。
夫の実家には、一人一台テレビがあるくらい、テレビがあって当然の家で育ってます。
そんな夫が、テレビのない生活に慣れることが一番の壁でした。
改めて私から夫へ説明、説得を行いましたが、根強い習慣に負け、もちろん理解はされませんでした。
ただ、説得期間が長期化してきた頃、一時的に配置したTVを付けるたびに、私の視線が気になり、最終的には夫自ら「TVをなくそう!」と言ってきました。
結局は、根比べでした。
褒められた方法ではないと思うのです、参考にはしないでくださいね(;´・ω・)
ただ、当時の状況を振り返ると、平日はワンオペ。土日は夫が子を膝にのせてTVを見る。
土日になっても変わらない私の負担。。
夫育ての観点でも、我が家にはTVがない方が良かったのだと今振り返ってみても思います。
ちなみに、テレビをリビングから撤去した後、夫は抵抗を見せたいのか、子を膝の上に乗せ、携帯で一緒にYouTubeを見ている時期がありました。
ただ、次第に、子は夫の携帯を見ると、TouTubeを見せるよう泣き喚き、
更に、夫を見ただけで、YouTubeを見せるよう泣き喚き、
更に更に、「夫」=「YouTubeを見せてくれる人、一緒に遊んではくれない人」
と認定されたことに夫自身が気が付き、YouTubeを見せることをやめたようです。
妻による説得よりも、子の態度の変容の方が効果があったのでしょうね。
夫婦関係が絡むと、テレビやYouTubeの視聴時間問題はなかなか難しい問題だと実体験をもって感じています。
最後に
テレビを配置していない家庭は、決して多くはないですが、稀でもないと思ってます。
実際、私の知人やにも数人います。
子にテレビを見せたくないと思い始めている方は、ぜひ一度、リビングにテレビはあって当然という思い込みを捨て、完全にテレビと決別する生活を想像してみてほしいと感じます。
その際、少しずつでいいので、夫婦でテレビに関する意思のすり合わせは必要です。
個人的な考えとしては、子育ての方針は夫婦で完全に一致している必要はないと考えますが、
テレビに関しては、一致させとかないと後々、夫婦喧嘩の種になりそうです。
便利なはずのテレビ。
子育て上、テレビが悩みの種になり始めたら、思い切って切り捨てるのもありだと思います。
現時点で3年程、我が家にはテレビはありませんが、少なくともあと3年は必要ないです。
テレビがないことで育児が楽になったお話を以下にまとめてますので、良かったらどうぞ。
子が小学生になり始めたら、テレビ再配置を再検討しようとは考えてます。
(あくまで再検討なので、再配置する可能性は低い気がする・・・)
最後まで読んでくれてありがとう!
Have a good day☀
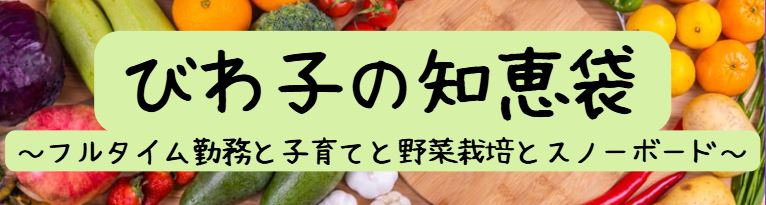




コメント