娘は、ブラウント病と診断され、2歳から装具を日常的に装着しています。かれこれ2年ほど装着していますが、装具治療をしていく中で大変な事が多くありました。しかし、大変な反面、結果的に身についた事や学んだ事など、ブラント病になったからこそ得たこともある、と最近気がつきました。病気を診断され、ネガティブ感情が止まらない方が前向きになるきっかけになれば幸いです。

ブラント病を診断され、装具治療を開始した2年前は、病気によるプラスの影響など、考える余裕は全くありませんでした。
振り返って見ると、やっと最近、視野を広げて物事を捉えられるようになったのかもしれません。
日常下では病気と向き合っていかなければなりませんが、日常の細部から少し離れて俯瞰して見ると、負の感情にとらわれずに、現状を捉えることができつつあります。
本記事の大部分はブラント病に限った内容ではないので、ご自身が関わっている病気を一歩引いて見るきっかけにしていただけたら幸いです。
【影響①】2歳児イヤイヤ期に装具装着した経験により、母である自分に圧倒的な忍耐力が身に付いた
「子どもにイライラしないの?感情的に怒ったりしないの?」
最近、うちと同年齢の子どもをもつ友達によく言われる言葉です。
この言葉により、自分に忍耐力が以前より身に付いていることに気がつきました。
現在、第一子4歳児で謎のこだわりと自分ルールが多い時期、そして、第二子2歳児でイヤイヤ期。
二人とも手がかかるこの時期にフルタイム勤務をしており、日々時間に追われていますが、私が感情的に子どもに怒ることは、月に一回もないです。
怒鳴ることは一年に一回もないです。
理由は単純で、もっと遙かに大変だった時期が過去にあるからだと考えています。
それは、今から2年前、第一子2歳児イヤイヤ期の子に装具装着という難題、そして第二子生後6ヶ月でまだまだ手がかかる、更に、自分が産後6ヶ月で体力が回復しておらず体が思うように動かない、更に更に、夜泣き対応で寝不足の日々、、、思い出しただけで実に壮絶でした。
今後、当時を上回る程に余裕のない時期が来ることは滅多にないのかなと想像しています。
2歳児イヤイヤ期の装具装着の様子は以下にまとめてますので、良かったらご覧下さい。
その大変な時期は1年ほど続きましたが、当時は自分に本当に余裕がなく、強制的にキャパを広げられました。
そして、ちょっとしたイヤイヤでは動じない忍耐力が付いたと自分でも思います。
装具装着の経験がなければ到底身につかなかった力であり、環境が自分にそうさせたと感じています。
当時を思い返すと、現在の第二子イヤイヤ期はかわいいものだと思います。
2年前の必死の期間がなければ、当時もっと育児を楽しめたのかもと思う事がありますが、この装具治療のおかげで、その後の育児を楽しめる余裕が生まれた事も事実です。
【影響②】親子で力を合わせて乗り越えた経験が絆となり、大きな自信に繋がる
2歳児イヤイヤ期の装具装着は、結果的に私に忍耐力を与えましたが、2歳児イヤイヤ期の子に装具装着という難題をその忍耐力により乗り越えたわけではなく、私と娘で力を合わせて乗り越えたと感じています。
私の声がけで娘が頑張った時もありますし、娘が踏ん張れない時は、私が気分転換のきっかけを用意し、気分が乗れる環境を作って、再度チャレンジしていました。
私にできることは、娘を信じ、気分転換のきっかけや環境を作ることでしたが、それらを娘はなんとなく理解してくれて、応えようと努めていました。
自分で頑張れないときは「ママお願い、どうにかして」と少ない言葉でも泣きながら訴えてくれました。
幼児期の親子関係は時に上下関係のようになりがちですが、一つの難題に親子で取り組むことで、同じ目線になれ、親友のような絆が育まれた気がします。
余談ですが、装具治療により我慢していることが多いので、装具以外で我慢することを出来るだけ少なくするために、私は娘の我慢に敏感になりました。
言葉を明確に話せない2歳時期でしたが、目を見て話す機会が増え、娘が嫌がっている時はもちろん、我慢している程度の機微にも以前より気がつけるようになりました。
装具以外で我慢することを減らす一環で、我が家にはテレビを置いていません。
装具治療開始した時点で既にテレビを置いてませんでしたが、テレビを置いていると親が視聴時間を抑制するタイミングが少なからず発生します。
テレビ自体なければテレビを見たいのに消されてしまって我慢しているという感情すら起きず、それで泣くこともありません。
そして、強制的に親が子と遊ぶ機会も増えます。
こう書いていると、ストイックなように見えますが、テレビを配置しない方が育児は楽だと思っています。
それについて下記記事にまとめておりますので、良かったらご覧ください。
【影響③】少数派であることや人と違うことを恐れない
人は、マイノリティの要素や人とは異なる特質を何かしら持っています。
長い間ずっと多数派に属していると、自分が人と異なる状態になることに対し免疫がつかず、受入れられなかったりするのかなと私は考えています。
人と違う状態とは、例えば、病気関係では、娘のように装具を付けたり、視力が悪く眼鏡をかけたり、外見では、太っていたり痩せていたり、髪の毛が天然パーマだったり剛毛だったり。
娘は、保育園のクラスが20~30人弱、保育園全体200人の中で、自分一人だけ装具を付けています。
4歳の現時点までは、自分だけ装具を付けていることに対し、「他の子は装具付けていないのに自分だけ…」といった負の感情を抱いている様子は見たことがありません。
一般的に、他者と自分を比較するようになるのは4歳頃と言われているので、そろそろ自分だけ装具を付けていることに気がつき、何かを感じ取る頃です。
今後、娘が自分と他者を比較し、人と違うことに気がついた時に、
「私は足が悪いから、装具を付けてるのよ」
と臆せず、恥じらわずに言えるようになって欲しいなと思ってます。
その為には、装具を付けていることを親が隠したり、恥じらったりすると、子はそれをすぐ察知し、時には真似しますので、そういった感情すら私自身持たないようにしようと決めています。
そんな願いの下、装具を付けているという見た目上、明らかなマイノリティでいることは、貴重な機会だと捉えています。
【影響④】県立こども病院で、重症患者のこどもや赤ちゃんに出会う
県立こども病院は、乳幼児期の重症患者が多く通院、入院している施設です。
日常生活では出会うことが滅多にないような、一目で何かしらの病気や障害なのだろうと分かるような子どもしかいません。
装具治療している我が子もそのうちの一人で、通院の際は、装具等の医療器具を付けている子と沢山すれ違います。
大人の私ですら、色々と考えさせられますし、娘はそういった子をまじまじと観察しています。
娘が幼いながらにどんなことを感じているのか分かりませんが、そのような子を特集したドキュメンタリー番組を見るのとは全く異なり、間近で見ることで、症状の様子、表情、感情などが温度感と共に伝わってきます。
番組の視聴者など外野からみると「可哀想」という言葉が出てくると思いますが、病気は違えど当院に同じく通院している当事者になると「可哀想」という類いの言葉や感情は全くありません。
ただただ生命を大事に、必死に治療を行い、病と闘おう、といった、ある意味、エネルギーに満ちた空間だと感じています。
私は通院時、病気と闘っている親子を多く目にすることで、病気のような大きな壁にぶち当たっても、目を背けずに信じて対処することが大切であると親子で学ばせてもらっています。
【影響⑤】体が柔らかくなる
装具を付けて地べたに座る際、正座はもちろんのこと、お姉さん座りやあぐらをすることはできず、基本的に開脚で座ることになります。
その為、座っておもちゃで遊ぶ時は開脚して座り、足の間および体の正面におもちゃを置いて遊びます。
その体勢から容易に膝を曲げることはできないので、開脚で強制的に足を伸ばしている状態となり、結果的にかなり体が柔らかくなりました。
弟と比較すると一目瞭然。
今後どんなスポーツをするにしても、体が柔らかい事はプラスに働くと思うので、良い影響だと感じています。
【影響⑥】保育園の同じクラスの保護者に覚えてもらいやすい
他の保護者に覚えてもらったからといって何があるわけでもないですが笑、保育園の送迎時に時たま会話する他のママさんに対し、私がどの子の母なのか、すぐに分かってもらえて、自己紹介がスムーズです。
はじめは自覚がなかったのですが「装具付けている子のお母さんですか?」と聞かれることが多いことに気づきました。
他のお母さんからすると装具を付けている子が同じクラスにいるということは気がついているものなのだと分かりました。
以降は、「装具を付けている子の母です」と言うと、その後の話がスムーズなので、時々使ってます。
最後に
ブラント病に関して、大変だった話や苦労話の記事が多くなってしまったので、今回は、子育て上および私にとってプラスに働いた内容について記事にまとめました。
プラスの内容に絞って記載したので、きれい事のように思われてしまう懸念はありますが、無理にプラス思考に転じようと努力した訳はなく、本心をまとめてます。
今後、娘の治療を続けて行く中で、手術時など苦しい場面で視野が狭くなったら、本記事を読み返し、視座を上げるきっかけにしたいなと考えています。
一緒に乗り越えましょう。
今日も素敵な一日になりますように☀
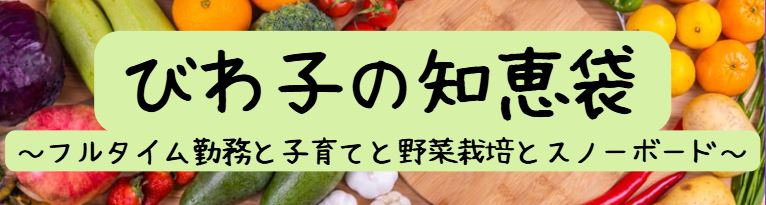





コメント